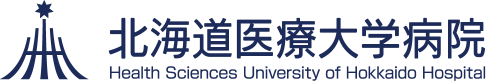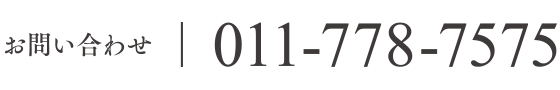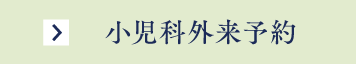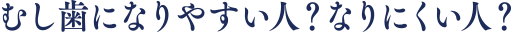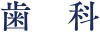- ホーム
- 〉
- 診療科・部門のご紹介
- 〉
- 歯 科
- 〉
- 小児歯科
小児歯科

- 月~金曜 AM 8:45~11:30/PM 1:30~5:30
※歯科の午前の診療開始は9:00、午後の診療開始は13:30からです。

- 小児歯科医長/大友 麻衣子
お子さまのむし歯やかみ合わせなどの相談や診断・治療を行います。また、歯みがき指導、歯質強化などにより、お子さまの口の健康を守り、むし歯などを予防して、口と歯の健全な成長と発育を支援します。
お口の中の衛生状態、歯並び、歯の質や生活習慣などによってそれぞれのリスクは違います。むし歯菌の多い人、唾液に粘性があり量の少ない人、歯の質が柔らかい人などは、むし歯になりやすい人です。もともとむし歯菌は、生まれたばかりの赤ちゃんには存在しません。むし歯菌は生後2歳~3歳の頃に子どもとのキスや、口移し等によって大人から感染します。また、サラサラした唾液は食べかすを流してくれますが、体力が低下したりストレスがあると唾液は粘りを持ち量も減ります。
つかまり立ちや歩行運動を学習する1才~2才のころは、身体の円滑な動作や反射経路が十分発達していないために転倒しても手で支えられず顔面を強打しやすい時期です。さらに学童期に入る頃は、遊びやスポーツに熱中するなどして外傷が多くなる時期です。
歯を打った時は、歯が欠ける、折れる、ぐらつくなどの症状や歯肉、唇からの出血を確認しすぐに歯科医院に電話して、なるべく早く受診してください。受傷状態によって処置が異なりますが、一般に来院までの時間が、処置や予後に大きく影響します。また歯が抜け落ちてしまったときは、乾燥させないことが重要です。受診するまでは、洗わずにそのまま牛乳で保存してください。30分以内に元の位置に戻して固定処置を行えば、予後も比較的良い結果が得られています。受傷した歯は、数か月後に変色したり痛みが出ることもあるため定期検診が必要です。また乳歯の外傷では、後継永久歯の発育や萌出に影響がある場合もあり、萌出終了まで長期間にわたり経過観察を行っていく必要があります。いずれにしても歯をぶつけるような怪我をした場合は、迅速な処置が大切です。
むし歯予防と言われて最初に浮かんでくるのは、歯みがきでしょうか?勿論これらは、むし歯予防には重要な役割を果たしています。しかし、むし歯になりやすいかなりにくいかは人それぞれ違います。歯並び、食習慣、生活習慣などお子様を取り巻く環境によっても変わってきます。
(1) フッ素塗布
年に3回~4回(3ヶ月~4ヶ月に1度)、高濃度のフッ素を塗布します。
(2) フッ素洗口
フッ素溶液でうがいをする方法です。ぶくぶくうがいが上手にできるようになったらご家庭で毎日出来て、安価でむし歯予防効果の高い方法です。


これらの、方法でむし歯予防を行っておりますのでお気軽にスタッフにお尋ねください。
「PMTC」という言葉を耳にしたことありませんか?
PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)とは簡単にいうと、歯科医師・歯科衛生士などのプロがお口のお掃除をするということです。
自分で行う歯磨きでは落ちない歯の汚れを歯科医院で専用の器具を用いて、きれいにクリーニングすることです。
↓
定期的に行うことによって、むし歯や歯周病の予防に大変、効果的です。
むし歯の予防として
- →
- 歯磨きでは落とせない、むし歯の原因になる細菌のかたまりを落とします。
きれいになったらフッ素を塗っています。
自閉症・ダウン症・脳性麻痺・知的障害など生まれつき又は事故などによって病気や障がいをお持ちの方々に出来るだけ苦痛の少ない歯科治療を提供するために (1) トレーニングを重ねて治療を行う。(2) 全身麻酔で治療を行うなどの方法があります。
(1) トレーニングを重ねて治療を行う方法
一般に歯科治療は不快なイメージが強く、特に障がいをお持ちの方は音や光に敏感だったり初めての体験に恐怖を感じたりします。そのような感覚を徐々に取り除き、環境や機械・器具などに慣れていただく様にトレーニングを重ねながら治療を進めてゆきます。
(2) 全身麻酔
全身麻酔で歯科治療を受けるとはあまり馴染みがないかもしれませんが、意識が無く痛みや恐怖心を感じることなく治療を受けることができます。勿論、治療中に体を抑えるなどの抑制はまったく必要ありません。
どの方法を選ぶにも十分な相談と、実際に治療が終了した後に新しいむし歯を作らない、歯周病にならないための予防が重要です。治療終了後は、定期健診を受けられることをお勧めいたします。
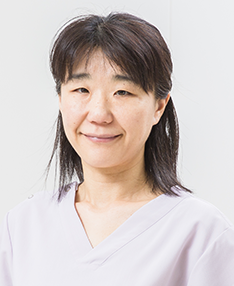

小児歯科医長
歯科医師大友麻衣子(おおとも まいこ)
- 所属学会・資格
- 一般社団法人日本小児歯科学会認定小児歯科専門医
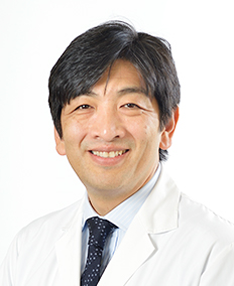
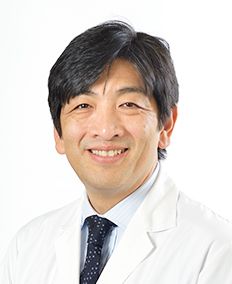
歯科医師齊藤 正人(さいとう まさと)
- 所属学会・資格
- 一般社団法人日本小児歯科学会認定小児歯科専門医


歯科医師倉重 圭史(くらしげ よしひと)
- 所属学会・資格
- 一般社団法人日本小児歯科学会認定小児歯科専門医


歯科医師藤田 裕介(ふじた ゆうすけ)
- 所属学会・資格
- 一般社団法人日本小児歯科学会認定小児歯科専門医
歯科医師髙藤美帆子(たかふじ みほこ)
- 所属学会・資格
- 一般社団法人日本小児歯科学会認定小児歯科専門医
歯科医師蓑輪映里佳(みのわ えりか)
- 所属学会・資格
- 一般社団法人日本小児歯科学会認定小児歯科専門医
歯科衛生士猪股 理恵(いのまた りえ)
歯科衛生士伊勢 珠美(いせ たまみ)